アメリカにいた頃は
「今日も忙しかったわね、お疲れ様」
「オーナー、夜は眠れてます?」
「ええ、カフェが忙しいのはいい事ね、疲れてぐっすりよ」
「そうですね、オーナーも帰り道は気をつけて」
「じゃ、また明日、Shintaroさん、安全運転でよろしくお願いしますね」
二人はゆっくりと重いエントランスの扉を閉めて歩き始める、が、Nanaが立ち止まり無意識に振り返る
「どうした?心配?」
「ちょっと、気になっている事があって」
「うん、わかってるよ」
「オーナーはもっと色々、知っているはずよね」
「そうだね」
「あの、止まらない涙の理由はもっと悲しい出来事があったのかな」
「たぶんね、今はまだ、混乱もあるだろうし、そんなに簡単にはいかないだろうと思うよ、少し時間が必要だろうね」
「そうよね、私達はこれまで十分過ぎる時間があったから、でもオーナーはそうじゃないものね」
「さぁ、車乗って、行くよ」
乗り心地良いシート、優しい香りがする、なんの香りだろう
「この曲、懐かしいね」
「ああ、これアメリカにいた頃、流行っていたな」
「ちょうど、ダウンタウンから帰る道、あの橋を渡る時にこの曲がかかっていて、夜景が綺麗だから」
「思い出した?」
「うん、あの道好きだったんだよね、今でも橋からの景色は記憶が鮮明にあるのよ」
「そういえば、Cafe Metro でよく待ち合わせしたね」
「そそ、まだあるのかな?よくお茶したよね、あの頃、大学の同じMajorにカッコイイ人がいてMetroでよく見かけて」
「あはは、あの話し?Mikeだったっけ?」
「うん、ちょっと話す機会があって段々仲良くなって、今週末はMetroで会おうねって言われたから、誘われたのかと思って」
「で、行ったら彼は来なかったって話しでしょ」
「そそ、でさ、めっちゃ綺麗な彼女がいたんだよね、ああ~もう、変な事思い出しちゃった」
「ま、軽く挨拶みたいな感じで言ったんだろうね、ちょっと自意識過剰だったんじゃないの?もしかしてって」
「え~そんな事思ってないもん、感じ悪~い」
「ごめん、ごめん、でも、アメリカにいた頃はもっと尖っていたよなぁ」
「そうかな?まあ、精神的に自由だったって事かな」
「毎晩、遊び歩いて勉強してなかっただろ?」
「全然、遊び歩いてなんかいません!」
「あはは、はいはい、そういう事にしときますか」
「ねえ、そのさ、頭ぽんぽんって子ども扱いしないでよね、歳だってそんなに違わないんだから」
「ん?不満?まあ、精神年齢が低いから仕方ないだろう?」
「もう、明日から絶交する、コーヒーもセルフでどうぞ」
「あはは、うそうそ、冗談だって、Nanaからかうのは面白くってさ、つい」
重く圧し掛かる不安を感じている心とは裏腹に、それを消し去るように明るく振る舞う二人なのでした

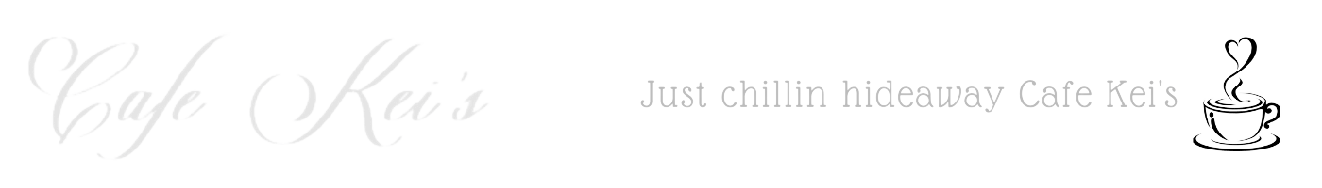
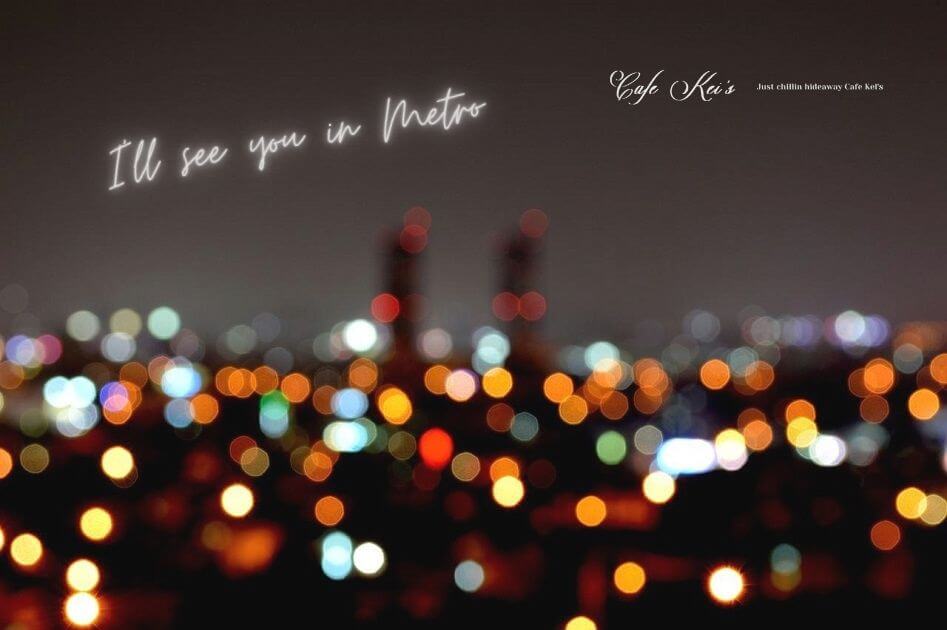
コメント